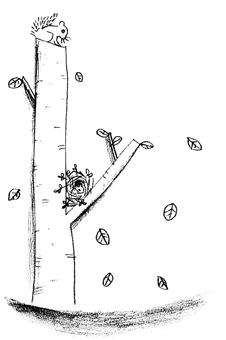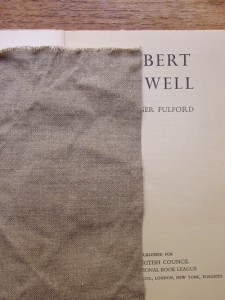* 近所の川で 鹿に出会う
2011/09/21 | Filed under 動物 | Tags シカ.これは 今年の7月の話なのですが、家の近くの川べりを散歩していると、鹿がいました。
川べりにしげった夏草を、鹿は もぐもぐ食べています。体の大きさと、つのがないことから、おとなのメスのようだと思いました。
この川は、身近に自然に触れられる場所ではありますが、鹿のいた場所のすぐ上には、わりあい大きな橋があって、比較的交通量の多い道が通っています。また、至近距離には、ショッピングセンターなどもあります。川べりの遊歩道(鹿のいる所よりも高い所にある)は、散歩している人や犬も多い場所。山の中ではないので、さすがに鹿はちょっとめずらしいのです。
それから、何日かすぎても、まだ鹿はそのあたりにいました。あたりの草が倒れて、明らかにそこで寝たとおもわれる場所や、ケモノ道みたいなのも出来ていて、ずっとそこに滞在しているようです。
鹿は基本的に群れる動物だということなので、一匹でいるというのは、迷子だろうか?とちょっと心配になりかけていたところ、ガサっとしげみから、もう一匹出て来ました。子鹿のようです。つまり親子?
わたしがじーっと見ていると 鹿たちは、視線に危険を感じたのか、いきなり川をピョンピョーンと渡って(水深50cmくらい)向こう岸の背の高いオギのしげみにかくれてしまいました。けっこうな距離を一瞬で移動する素早さにはびっくり。
しげみにかくれると、まったく姿が見えません。ただ、草の上の方がガサガサと 風に吹かれているのとはちがう動きをするので 鹿が動いているとわかりますが、止まってしまうと、見つけるのはまず無理。自然界の中で、動物達は、おたがい こうやって身をかくしながら 生きているのだなと あらためておもいます。
その後も、そこを歩くたびに鹿に会うことができ、鹿たちは、すくなくとも2週間以上は そのあたりに滞在していたようですが、台風の接近を境に 姿が見えなくなりました。天気の変化を察知して、山に戻って行ったのでしょう。
夏の終わりになって、川べりの草は 炎天下に晒された結果、堅そうですし、枯れたり、虫食いがあったり、かなり傷んでいます。鹿が川べりにいた夏のはじめは、川べりの草がいちばんみずみずしくて美味しい時期だったのかな、とも思います。
* 日本みつばちの養蜂見学
2011/09/17 | Filed under 動物 | Tags ミツバチ.近所の川べりのヤブカラシ(ぶどうの仲間)は、今 花盛り。目立たない花ですが、日本みつばち(上の写真左)やちょう、あしながばち、それにおおすずめばち(写真右)までもが たくさんあつまっています。
去年の夏の思い出なのですが、機会があって、日本みつばちの養蜂を見学させていただきました。
日本みつばちが なんだか気になるようになったキッカケは、わが家の表の花壇に植えている「カラミンサ」の花にいつも、みつばちがいっぱいあつまってきていたことから。あるとき、 それは、養蜂で飼われる西洋みつばちではなく、日本に昔からいる、野生の日本みつばちだと知りました。
ここ数年、アメリカやヨーロッパを中心に、養蜂業で飼われている巣箱のみつばちが、わずかな幼虫と、大量の蜜をのこして、ほとんどいなくなってしまう「大量失踪」がおきているそうです。
ネオニコチノイドという昆虫の神経に作用する農薬の影響でみつばちが巣箱への帰り道を忘れてしまうとか、ミツバチヘギイタダニの被害や気候変動とか、原因はいろいろな説があり、はっきりとはわからないもよう。
その話を聞いて、始めて知ったのは、養蜂として飼われる「西洋みつばち」というのは、元はアフリカにいた野生のみつばちを改良して作った「家畜」だということ。
その家畜のみつばちに、アメリカではアーモンドやメロン、各種ベリー類など、実をつける作物の大規模農業(トウモロコシなどイネ科の風媒花を除く)は、みんな西洋みつばちに受粉を頼っています。アメリカには、もとはみつばちはいなかったので、先住民(インディアン)は、みつばちを「白人のハエ」と呼び、みつばちが飛んで来ると、やがて白人がやって来る不吉な知らせと受けとっていたとか。
アメリカやフランスなどでは、徹底的に効率を追求して管理された西洋みつばちと共に、工業のように管理された大規模農業が一緒に発達してきたので、今、そのみつばちに急激な異変が起きていることが、欧米を中心に、大問題になっているそうです。
日本の西洋ミツバチ養蜂でも、実際に養蜂家の方にお話をお聞きすると、割合としては少ないけれども実際に失踪も起きているようで、いちごの受粉用の西洋みつばちが足りないという事が起きるなど、兆しがあるそうです。
そのような中、日本には、野生の「日本みつばち」がいて、わたしたちのような都市生活者が ふだん身近に見かけるみつばちは たいていが日本みつばちなのです。
西洋みつばちと日本みつばちは、慣れると比較的すぐに見分けられます。おなかのしましまがわりとくっきりと見えて黒っぽければ日本みつばち、しましまがぼんやりぼやけていて、おなかがオレンジ色であれば、西洋みつばちです。ただ、わたしの家の近所では、西洋みつばちは 見かけたことがありません。近所に養蜂所がないのだと思います。
日本みつばちは、江戸時代までは養蜂で飼われてもいたのですが、西洋みつばちと比べ、はちみつの生産量が比較にならない程少ないという理由から、養蜂産業の中では、明治のはじめに西洋みつばちが導入されて以来、ほとんど飼われて来なかったそうです。
農業地帯では農薬の影響が避けられないのに比べて、逆に農薬の影響がほとんどない都市部は、今、日本みつばちにとっては 意外と暮しやすいのではないかと言われています。野生の蜂なので、空き家の屋根裏、木のうろ、お墓の納骨空間など、狭い隙間があって中に空間があるような所があれば、どこにでも巣を作れるので、都市部でも生きていけるのです。
西洋みつばちの方は、人の手を離れると、1年も生きていけないのに比べて、野生の日本みつばちは、たくましく生き続けていて、さまざまな植物の受粉を手助けてくれています。日本の野山や、畑は、日本みつばちがいて 成り立っているというわけなのです。そして、海外でみつばちの大量失踪が起きて、このままでは農業へのダメージが甚大になる、、とさわがれているとき、心配しながらも、「でも 日本には野生の日本みつばちがいるしね」と 落ち着いていられるというわけ。
そう考えると 日本みつばちが とても愛しくなってしまい、ひょっとして、うちにも日本みつばちの巣箱置けたりして?!とも思ったのですが、実際の養蜂を見学すると、やっぱり、うちのような住宅街ではとても無理ということがわかり、自宅に巣箱を置くという案は廃案になりました。
で、とりあえずは、みつばちのあつまってくるカラミンサを、3株にふやしてみたりしています。
日本みつばちの蜜は濃厚で、しかも野山のいろんな花から採取する百花蜜なので、味もさまざまです。お邪魔した養蜂園さんの蜜源にはミカンの花などがあるそうで、柑橘系のさわやかな風味がありました。また、日本みつばちの蜜は、蜜が 長い時間をかけて 少しずつ発酵するので、あの濃厚な風味になるのだそうです。
↓たっぷり蜜がためてある巣 ↓日本みつばち
* 今日の大失敗:猫の砂でトイレが・・・
2011/09/14 | Filed under 猫 | Tags 吸水性ポリマー, 猫の砂.夏もおわりになって、京都ではまた 昼間は真夏日の毎日です。朝晩はすずしいので、まだマシですけれど、なんだか頭ははっきりしない日々がつづきます。
今朝、スッキリしない起き抜けの頭のまま、夫のお弁当に入れるおかずは あれとこれと・・・とか考えながら、猫のトイレを掃除したら、トイレが詰まってしまったのです!
うちでは、ふだん「ひのきの砂(トイレにも流せる)」というのを使っているのですが、切らしてしまい 流せる紙の砂というのを 一時的に使っていました。その砂は、よくふくらむので もともと詰まりやすい気がしていたので、流すときは少しずつ、といつも注意していたのです。けれども、今朝は 頭がぼーっとして、3箱のトイレの中の、猫がおしっこをして固まった所をいっぺんに全部流してしまったら、途端に詰まってしまって、なんとあふれ出てしまったのです(涙)
そして、詰まった所は、もう、何をしても駄目。
何度も何度も、自分で水をかきだして、バケツで勢いよく流すことを繰り返してみましたが、それも駄目。
で、汗だくになって、あふれた所を拭いていると、ゼラチン状の物質があるので、「ゼラチンならお湯で溶けるかも?」とお湯を入れようとしたら、夫が「実験してからの方がいい!」と後ろで叫んでいます。それで実験して、きれいな猫砂少量の一方にお湯、もう一方には水をかけると、お湯の方では、水以上の早さで水分を吸収して固まるということがわかり、すんでの所でセーフでした。
それで、頭の回転の遅いわたしは、ここでやっと、このゼラチン状の物質は、ふつうの食べるゼラチンではないことに気づき、猫砂の袋で原材料を確認すると「高分子吸水性ポリマー」と。。。
吸水性ポリマーってよく聞くなあ。そういえば福島第一原発で汚染水をとめるために投入したけど効果なかったっていうアレ?で、ポリマーが化学的にどういうものなのかは、おいといて、水の温度のちがいだけで、ずいぶん反応の違いがあるのがわかったので、何かこのポリマーを溶かすことのできる物質があるのでは?と思いつき、吸水性ポリマーの性質について、ネット検索してみました。すると、「ナトリウムで分解する」と書いてあります。
分解するといっても、実際には溶けているのではなくて、浸透圧で、ポリマーの内部に吸収されていた水が食塩側に戻ってくるという作用なのだそうです。でもとにかく、ポリマーは縮んで水の通りがよくなるはずですよね。そこをジャーっと流せば良いんじゃない?!塩分を配管に通すと言っても、下水なのでいつも塩分は多量に流れているはずだから、それは心配しなくてもよさそうと おもいました。
そこで、アロマ用の塩のストックを出して来て、ボウルで水に溶かして ものすごく濃い食塩水を作りました。何%っていうふうに測れてはいないのですが、塩1と水2くらいで、それでパーッとかきまぜてある程度塩が溶けたくらい、の食塩水です。なめてみると、海水などよりも はるかにしょっぱい、ふつうでは口にできないくらいの食塩の濃度でした。
そしてそれを、何度かに分けて、トイレに投入しました。全部合わせても1リットルくらいしか投入できてないと思いますが、投入して直後から、砂のカスみたいなのが浮上してきて、何となく効いているみたいです。
数分たって、こわごわ、流すスイッチを入れてみました。すると、ふつうに すう〜〜〜っと 流れてくれました!
この吸水性ポリマーは、猫の砂だけでなく、紙おむつやナプキンなどにも使われていて、あとで ゆっくりネットで見てみると、紙おむつを間違えて洗濯機に入れてまわしてしまい、配管にポリマーが詰まった、というときには、食塩を入れてください というメーカーからの提案もあるようです。(私的には、食塩をそのまま入れるより、水に溶かしてあらかじめ高濃度食塩水として投入する方が、作用が早いのではとおもいます、手前みそですが)
それにしても、こういう生活の中にある身近な化学物質は、食塩のような やはり身近にあって単純なもので分解、崩壊させることができるというのは たいせつなことだなと思いました。たとえば火は水で消えるとか、そういったことと同じだとおもいます。
詰まっているのがポリマーだとわかった時、何かすごい薬品でもかけないと、詰まりがとれないのかも、と一瞬心配になってしまったので、食塩で解決した というのは、ハッピーエンドでした。しかし、この騒ぎのせいで、夫のお弁当は作れず。(そのおかずは、私が食べよう)
↓おたすけ高濃度食塩水の残り(塩を入れすぎて完全に溶けてません)
* Black Potatoes
2011/02/26 | Filed under 本 | Tags .最近、絵本や子供向けの読み物ばかり読んでしまうのですが、この間、Susan Campbell Bartolettiという人の書いた「Black Potatoes」という本を読みました。

1845〜1850年に、アイルランドで起きた大飢饉のことを書いた、ジュニア向けのドキュメンタリー本です。
「Black Potatoes」(黒いじゃがいも)というのは、1845年に、アイルランドの農民たちが主食にしているじゃがいもが 菌による病気にかかり、ほとんど一晩で真っ黒に変色して腐るという状態になったことから、その飢饉が起きたため、このように呼ばれているのだそうです。
じぶんのための ノートも兼ねて、この本の内容を箇条書きにしてみます。
*1845年は夏頃から天候が不順で、雨が多かった。秋の収穫時期、畑に植えてあるじゃがいも、収穫を終えて貯蔵されているじゃがいものすべてが、一晩で黒く変色して腐ってしまった。この減少は、1845年1849年まで、毎年起きた。当時は原因がわからず、妖精のしわざなどともささやかれたけれども、今では、Phythophthora infestansという菌が、南アメリカから輸入された鶏糞系の肥料から移ったのではないかと考えられている。
当時、アイルランドの農民たちは、食べ物のほとんどをじゃがいもに頼っていたので、大飢饉が起きた。
*当時、アイルランド全体はイギリスの統治下にあり(現在は北アイルランドはUnited Kingdomに所属しているが、南アイルランドは独立している)アイルランドの土地の多くは、イギリス人が領有していて、農民には多額の賃料が課せられていた。賃料が払えないと、土地を追い出されて 家族ごと放浪の季節労働者になってしまった。飢饉が起きている間も、年貢の取り立てはやむことがなく、大量の小作民が流浪の民になってしまった。
*イギリス政府は救済のために、急遽アメリカから「インディアンコーン」というとうもろこしを輸入したけれど、とても固くて人間が普通に食べられる状態でなく、このコーンのせいでも多数の死者が出た。
*政府の対策としては 地主などが出資して作られている「Poor House」という一種の収容所に貧民を収容した。そこでは貧しい人に わずかな食料を供給するのとひきかえに、一日12時間以上の過酷な労働を強いたため、亡くなる人もあとをたたなかった。
*当時、イギリスの経済に対する考え方は、「Lesse Faire(Let it do)」(政府が介入しない自由経済を尊ぶ考え方)の思想が中心にあったので、アイルランドの窮状に対しての政府の動きは遅かった。けれども、民間レベルでのチャリティ活動が高まってきて、一番飢饉がひどい時期には、政府主導で「Soup Kitchen」という、スープとパンを1日一回ずつサービスする炊き出しをした。けれども、すこし飢饉がおさまる傾向が見えると、早々と炊き出しは終了。
*農民の主食であるじゃがいもが 腐って駄目になったために起きた飢饉だったけれども、飢饉の間、麦などの他の作物は豊作で、それらは、経済作物として、イギリスなどに運ばれていた。このように順調に収穫できた麦、大麦が飢饉にさらされている人々に供給されることはなかった。(だから、江戸時代に日本でたびたび起こった「凶作による飢饉」とは 少し性格がちがう。)
*飢饉による餓死のほか、腸チフスやコレラなどが蔓延し、飢餓で抵抗力を失った人たちは、大量死した。
*じゃがいもが食べられないので、人々はお金に変えられるものは何でもお金に変えて、食べ物を買ったけれども、追いつかなかった。それで、土地の賃料が払えなくなって、追い出されて すべての財産を失う前に、残ったわずかのなけなしのお金でもって、アメリカへ移民する人が大量に出た。
*アイルランドの貧しい人たちは、三等船室でアメリカに旅をした。衛生状態、食べ物も悪く、もともと飢饉で体が弱り、伝染病が流行っていた所から旅に出た人たちは、多いときは20%くらいが、アメリカに着くまでに亡くなった。
*飢饉にくるしんだまずしい人達のほとんどは、アイルランド語しか話せず、また文盲率も高かった。その人たちが、アイルランドを去ってから、アイルランドでは多くの古い伝承なども忘れられ、またアイルランド語を話す人の数が激減した。
*アメリカに移民したアイルランド系の人たちは、底辺の労働者として、鉄道の建設など、アメリカ合衆国のインフラ作りに大量の労働力を提供した。
*現在、アイルランドの人口は、「黒いじゃがいも」飢饉の起きる半分程度しかいない状態。
だいたい要約するとこんな感じです。
移民をするとき、一族の中で別れ別れになるということも多く、たとえば10代の息子一人を残し、未亡人の母親が幼い子供達を連れてアメリカに移住するケースもあったそうです。
残る人びとは、移民する人と もう生涯会えなくなるという意味をこめて、お葬式と同じような方法で送る会をしたそうです。それは、涙とともに、 みんなで踊って 歌って、という会でした。そして、去る人が出発する際、残る人は、ギリギリ行ける限りの所まで 歩いて見送ったのだそうです。
それから、アイルランドの窮状が伝わると、1846年ごろから、アメリカからもアイルランド系の人などが、祖国にたくさんの寄付を送るなど、寄付が届いたそうですが、その中で、1838年にアメリカで大きな迫害にあった先住民、チェロキー族の人達(Trail of tears, 涙の道 で有名な オクラホマへの強制移住でたくさんの人が亡くなった)からも、飢饉で苦しむアイルランドの人へ、寄付が贈られたのだそうです。
この本の本文最後のページ (p172)には 以下のように書かれています。
****
アメリカに移住した多くのアイルランド人は、決して故郷を忘れようとせず、またその民族意識とプライドをもちつづけたのでした。
飢饉のときに、両親に連れられ移民した、ヴァージニア州リッチモンドに住むある男性は、言いました。
「私がアイルランドを去ったとき、まだ赤ん坊でした。アイルランド人たちは、とても大変なおもいをしたのです。でも、私の母はいつも、アイルランドの青い山々や、湖のことを話し、それらを愛し続けていました。家の中で、母はいつもアイルランドの歌を歌っていたものです」
* どうぶつの絵かきはじめたら
2011/02/26 | Filed under 動物 | Tags リス.「野の花えほん」のシリーズのつぎの本は 身近などうぶつ(と 小鳥、身近な生き物を少しずつ)の本を作らせていただけることになり、去年の夏ごろから 文章やラフの作業をしてきて、この間から すこしずつ 絵を描き始めました。
描いていると すごく感情移入をしてしまいます。犬のページなど、忠犬ハチ公の原稿を書いているだけでも、泣けてきます。淡々と ハチのエピソードを短く紹介しているだけなのですが。淡々とした その事実に すごく大きな何かがつまっていて、泣かされてしまうのです。
つきのわぐま、ひぐまの所では、小さくてかわいらしい絵ながら、マタギやアイヌのくま猟のイメージ画。
正直のところ、猟のイメージというのは、あまり描きたくはないのですが、でも、祖先にとってのくま猟は、生活であり 自然の一部だと感じます。この本では、動物の生物学的な情報だけではなくて、人との関わりや文化的な部分にも紙幅のゆるすかぎり 触れたいので、やはり描かないと。と思います。
以前「かやねずみ」を描くために、上野動物園に行きました。雨の日の動物園、とてもしずかでした。
上野動物園の入り口近くにいたのが、日本リス。日本リスは、京都の動物園にもいるので、ときどき会いに行きます。夏毛のときは手足がオレンジ色で、それはそれは美しい動物。ペットのシマリスにくらべて、日本リスは少し大きいし、筋肉質な感じもするので、可愛く描けるかな・・・と心配していたのですが、ほんものの日本リスをひとめ見たとたん、その美しさにすっかりめざめてしまって、いま、わたしのなかで「もっとも絵になる動物」のひとつが、日本リスです。
* here comes the rain again
2011/01/11 | Filed under 音楽 | Tags アニー・レノックス.You Tubeで なつかしい曲をみつけました。
80年代、イギリス発で活躍したユーリズミックスの[Here Comes the Rain Againという曲。もともとユーリズミックスはテクノっぽかったのですが、このライブ版はアコースティックで 個人的に好みです。(アコースティック好きなので)
ユーリズミックスの後、ボーカルのアニー・レノックスはソロで活動しています。イギリスではたぶん、和田アキ子さんとか 八代亜紀さんとか すでにそういう存在なんじゃないかと思うのですが、去年くらいにテレビ出演して、同じ曲を歌っている動画も、You Tubeにアップされていました。年を重ねて「素敵なおばちゃん」みたいな雰囲気になっているアニー・レノックスの姿に 時の流れを感じつつ、より しみじみと歌い上げる歌声にはやっぱり感動です。
そのトークでの思い出話では、この曲は、ユーリズミックスのパートナーだったデイヴ・スチュアートとニューヨークに行った時、セントラルパークにいて、なんだかとても寂しい気持ちになって ふと出て来たメロディだったとか。小さなキーボードだけで、作曲したのだそうです。
You Tubeってほんとに何でも見られるなあと、ちょっとうれしくなって itunesでも検索したら、このアコースティックなライブ版、売ってるじゃありませんか。でも、この曲だけでは買えず、アルバム全部買わないと駄目ですって。。。えーと、来月にしよう。。。
* Rue de Renneという生地
2011/01/07 | Filed under リネン | Tags .LINNETで’Rue de Renne’というなまえで販売している、定番のリネン生地。
今度から、日本国内で織ることになり、先日出来上がってきたのを さわってみて、ひさしぶりに リネンの生地にドキドキしました。
すこし厚地で、織り密度がやや高く、しっかりしているけれども しどけないリネンの質感もある、わたしにとって「これがリネンというものだ」と もっとも感じる、 いちばんベーシックなリネン。
このタイプのリネンに、わたしがはじめて出会ったのは、パリのレンヌ通りに昔あった、小さなメルスリーでした。
表にワゴンにのせてハギレが売られていて、そのなかに、こういうリネンがあったのです。
もう、16〜17年も前になるでしょうか。そのころは、日本国内では、リネンの生地というものが ほとんど流通しておらず、こんなベーシックなリネンの生地さえも、わたしにとってはめずらしいものでした。
素朴だけど、何となく高級感も感じるリネンの質感というものに、深く心を奪われたのは、そのとき その生地に出会ったのがはじまりだったとおもいます。リネンのもっている矛盾した2面性、粗野な感じと、エレガントさという、相反するものが同居している感じに 心のなかの深いところで 刺激されました。それは、たとえば文学とか絵とかに受ける刺激とほとんど同じ刺激だったとおもいます。
そのとき買い求めたその生地は、長い間引き出しにストックして、サシェとか、ティーマットのような小物づくりに、チビチビ使いました。
LINNETをはじめて、同じクオリティの生地が絶対ほしいとおもいました。最初は、たしかリトアニアからの輸入、そのあとは、ベルギーから輸入していました。そして、生地には、最初にそのリネンに出会った思い出の場所、Rue de Renneというなまえをつけました。
今回,日本で織ることになったRue de Renneは、織り段階からわたしたちの微妙なこだわりを、スパイス的に入れ込むこともできたので、わたしにとっては ほぼ完璧な質感が実現されています。
ちなみに、その小さなかわいいメルスリーは、その後大きくなって、今はマレ地区にあります。最近はよく雑誌にも紹介されていて、Fではじまる名前。。。(忘れたので、また思い出したら書きます。パリに詳しい方なら、みなさんご存知だとおもいますが)
* あけましておめでとうございます
2011/01/07 | Filed under 生活 | Tags .2011年 あけましておめでとうございます。
ことしが みなさまにとって おだやかで よいお年となりますように。
(写真は うちの猫 ふく「福」です。1997年10月生まれなので、今年の10月で14歳になりますが、
まだまだ元気で活発です。)
今年のお正月、 はじめて自分でおせち(とお雑煮)をつくりました。
母が作って じぶんが手伝うというのは 今までもありましたが、自分でつくったのは
うまれてはじめて。。。(この年になって)
やってみると とても楽しく、日本のお正月らしくて やっぱり良いなと思いました。
今までは、わたしが自分でおせちなんて作っても、ほとんど食べてくれる人もないし。と
思っていたのですが、これからは 毎年 作ろう。とおもいます。
* 野の花えほん 原画展
2010/12/27 | Filed under 本 | Tags .おとといから 本格的に冬がやってきたようです。
きのう 近所の川べりを歩いたら おどろくほど 水が澄みわたっていて
川底にしずんだ もみじの葉が 透けてみえました。
気がつくと もう年末ですが うれしいことがあります。
今日から 愛知県 豊橋市の書店さん、精文館書店本店3Fで
「野の花えほん」の原画を展示していただいています。
本のために描いた原画のなかから 8点を選びました。
みなさまに ごらんいただけたらうれしいです↓
2010年12月27日(月)~2011年1月26日(水)
お問い合わせ:精文館書店本店児童書(0532-54-2345代表)
* チッチ in the basket
2010/10/10 | Filed under 動物 | Tags .きのうは一日中雨。。。町内に住んでいる猫のチッチは、ほとんどバスケットの中で過ごしていました。
このバスケットは、最近うちのガレージに置きました。チッチは、去年、少し西の方から、うちの町内に流れてきた野良猫のトラ美ちゃんが生んだメス猫。同じときにオスのトラ次郎も生まれました。小さくて頼りない子猫2匹を連れたトラ美親子は、ご近所のみなさんに可愛がられるようになり、避妊去勢手術をして、今は定住しています。
もともと、チッチ親子のための寝床は、うちのお向かいのお宅の方が用意してくださっていました。今も、もちろんそこに箱があります。けれども最近、うちの北裏のお宅のあたりで生まれ育った、ジャンボと呼ばれる大人のオス猫がご近所さんたちの人気ものになり、特にお向かいさんのご家族にすごくなついてしまい、チッチたちの箱にジャンボが寝るようになったのです。
ジャンボは、体は大きいけれども甘えんぼうで、子どもの頃はちょっと気が弱くやさしい猫でした。じつは、うちの猫になったニャンカも、ほんの数ヶ月年上だったジャンボと知り合いで、ジャンボにはなついていました。チッチの兄、トラ次郎は大柄な堂々とした猫に育ち、ジャンボと仲良しで、同じ箱で寝たりします。男どうしでは、きっとジャンボはいい奴なのかも。
でも、トラ美ちゃんとチッチは、ジャンボとは特に仲が悪いわけではないのですが、ちょっとけむたいみたいです。少なくとも、同じ箱や隣の箱で寝ようと思う程に仲良しではないもよう。
とくに、チッチは、もう1歳半ですが体重2.6kgほどで、子猫とまちがわれるような小さな猫です。(子どもの時、栄養不足だったと思われる)小さくても勝ち気なチッチですが、ジャンボに大きな体で威圧的にふるまわれたりすると、やっぱり微妙に怖がっています。
お向かいさんに「最近ジャンボがあの箱で寝て、チッチたちは寝ないみたい」とのお話を聞いてから、これから寒くなることでもあるし、うちのガレージでも寝られるよう、かごを置くことにしました。
写真の右端に置いてある、もう一つのマルシェかごは、別のご近所の方にその話をしたら、ご厚意で持って来てくださったもの。チッチはこちらも気に入って、今入っているかごと交互に入ってみたりしています。また、このかごは少し大きいので、トラ美ちゃんや、みんなにガブちゃんと呼ばれている白黒猫なども時々利用するようになりました。
余談ですが、チッチは、お向かいさんでは、「バジル」というおしゃれな名前で呼ばれています。
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
New archive
BlogArchives:
- 2014 November (2)
- 2014 October (9)
- 2014 August (2)
- 2014 May (1)
- 2014 April (1)
- 2013 July (1)
- 2013 June (1)
- 2012 March (3)
- 2012 February (3)
- 2012 January (4)
- 2011 October (3)
- 2011 September (3)
- 2011 February (2)
- 2011 January (3)
- 2010 December (1)
- 2010 October (3)
- 2010 September (3)
- 2010 August (3)
- 2010 July (6)
- 2010 February (2)
- 2010 January (5)
- 2009 June (1)
- 2009 May (3)
- 2009 April (3)
- 2009 March (3)
- 2009 January (1)
- 2008 December (2)
- 2008 September (1)
- 2006 November (2)
- 2006 October (1)
- 2006 August (3)