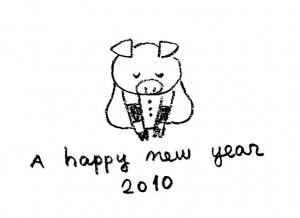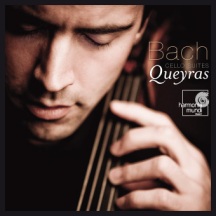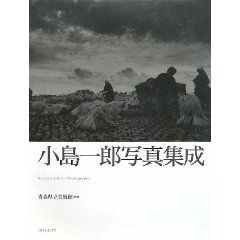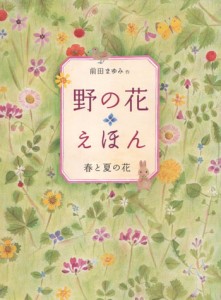* 2010年 あけましておめでとうございます
2010/01/04 | Filed under 生活 | Tags cat.うう~昨年も、ふたをあけてみれば後半にブログの更新がぜんぜんできませんでした。。。
自分で自分を分析してみると,キーボードで入力する文字の世界に入ると,なんとなくかしこまってしまうというのでしょうか。LINNETのお客様に毎月更新で発送時に同封させていただいているニュースレターは、未だに手書きで作っておりまして(じつは手書きしたものをスキャナでとりこんで、PCでレイアウトしたりしているのですが)、なんだかそちらの方は,リラックスして書けるので、いっそのこと手書きの画像をスキャンして載せようかなと思ってみたりしつつ、せっかくなので、もうすこしこのスタイルでがんばってみようと、気分を新たにしました。
こんなわたくしですが、みなさま どうか、今年もよろしくお願いいたします。。。
↓今年は虎年ということで、トラ猫の写真を。。。(じつは虎年でなくても載せたかったのでした。猫にご興味のない皆様,おゆるしを)
以前にLINNETのニュースレター「よもやまばなし」に書いた,のら猫親子の、子供たちです。(もう1歳弱ですが)手前がチッチ,2.6kgくらいのチビ猫です。うしろに控えているのが兄貴(弟かも?)トラ次郎。チッチより二回りも大きく,いつも妹(姉?)のごはんを奪う以外は、フレンドリーで性格のいい奴です。(photo by 夫)
* お医者さんのエプロン
2009/06/17 | Filed under リネン | Tags .先週できあがったばかりの,オリジナルプリントのエプロン。姫路の,くろさか小児科アレルギー科様からの特別オーダーでLINNETがお作りしました。
プリントからオリジナルで柄を起こして、エプロンの型も,今まで使われていたものを元に少し修正を加えて、あらたにパターンを起こして作ったものです。
柄を考える際にいただいたリクエストは、大きめの花柄で,所どころに,動物や小鳥などがこっそりいるようなのにして下さい、ということでした。病院にやってきた子供たちが,それを見つけて「あ!」と指差したりするのだそうです。そんな細やかな配慮に,とても感動しました。
こんな華やかなエプロンは,今回わたしたちが作らせて頂いたものでもう3代目とか。院長先生が渡英された時に、現地の病院で,明るい大きな花柄のカーテンがかかっていたことが印象的で、ご自分の病院でもぜひ、そんな雰囲気作りをしたいと思われたとのことです。
自分がお仕事させていただいたから,という訳ではなく,こんな素敵な病院があるということに,素直にびっくりしました。それと共に、こういう場に,絵を起用していただいたということが,とても嬉しく、やりがいを感じました。
* 高村智恵子の生まれた家
2009/05/25 | Filed under アート | Tags ねじばな.「野の花えほん」の「ねじばな」のページの取材で、昨年秋、福島にいきました。「ねじばな」の別名「もじずり」の語源になっている、福島県の「もじずり染め」というのが実際にどういうものなのか、わからなかったのですが、福島県にある「文知摺観音」というお寺を訪ねれば、復元した染め物や、もじずり染めに使った石などを見せて頂けるとわかり、訪ねることにしたのでした。それで描いたのが、もじずり染めの絵です。
そして、宿泊した旅館から車で30分程の所に「高村智恵子の生家/美術館」があるのを知り、取材をした次の日の朝、寄る事が出来ました。昔から高村智恵子の紙絵に惹かれていて、智恵子抄の他、「智恵子飛ぶ」(津村節子著)などの伝記も読んでいたので、かなり嬉しかったです。
裕福な造り酒屋だったという生家は、一時人手に渡ったそうですが(この実家の破産、没落が、智恵子の精神病の発症の引き金になった面があるようです)よく保存されていて、裏にはこじんまりした美術館があり、智恵子の紙絵の実物と、油絵が展示されていました。夫の高村光太郎によると、智恵子は油絵を描こうとして、努力を続けていたけれども、上手く描けないことに悩んでいたそうです。
わたしは智恵子の紙絵や、若い頃に描いた「青踏」という雑誌の表紙画を見ても、高村智恵子は グラフィックデザイナー的なセンスが秀でた人で、「平面」の表現の人だと思います。今で言うと、ブルーノ・ムナーリとか、そういったジャンルの仕事にとても向いていた人だと思うのです。
智恵子はどうして、油絵にこだわっていたのでしょう。油絵というのは、絵という平面に見えますが、わたしが思うに、実は「立体」に近い気がするのです。油絵の具は、水彩に比べると、粘土にも近く、この立体物をキャンバスにくっつけていく事で微妙な陰影や色や形が生まれます。ただ、ルネサンスとかファンアイクなどの時代には、油絵はもっと平面的なものだったかもしれません。でも、おそらくは印象派以後、油絵はどんどん立体的なものに発展したと思います。そして、パリ画壇の影響を受けた当時の日本の画壇の方向性もそういったものだったと思います。智恵子の残した油絵を見ると、モネやゴッホの絵のごとく、絵の具を立体的に盛り上げてありました。そして、光太郎が描き残すように、それはやっぱり「習作」の状態と見え、後に智恵子が作った斬新な紙絵の完成度とは違う次元でした。
ここでもうひとつ思い出すのは、油絵の顕著な特徴。絵の具が乾くのに時間がかかり、つまり作業に時間がかかることです。頭の中にあるイメージがあるとして、それを手でつむぎ出すのに、泥をこねて何日も格闘するような、そういう作業を経なければいけません。グラフィックデザインのように瞬時に、作りたいイメージに必要な色、形を取捨選択し、平面を構成してピタッと決める、そういう、ある程度「一発勝負的な」作業とはかなり違っています。智恵子は紙絵を作る時、色紙や包み紙をしばらく眺めた後、ほとんど迷うことなくハサミを入れて、かなりの速度で作っていたそうです。デザインという作業の中に先天的にある潔さ、それが智恵子には備わっていたように思えるのですが、その潔さは、油絵の具の可能性を追求しながらドロドロになって格闘していく油彩とは、相容れないものだったのかもしれません。もしかすると、現代の、すぐに乾くアクリル絵の具を彼女が手にしていたら、絵画的な表現をするにしても、何かが違っていた可能性もあると思います。
智恵子はグラフィックデザイナー的才能の人であり、油絵は向いてなかった。そんな単純な事実が そこにあったのではないかと思います。けれども、彼女がその縛りから抜けられなかった理由は何だったのか。彼女自身がこだわる性格だった、高村光太郎が「立体」の人だったという影響、当時の画壇の雰囲気。。。いろんな理由があるのかもしれません。
狂気の中で、始めて彼女がその縛りから解放され、最晩年の短期間の間に、おびただしい数のあの美しい紙絵作品群を作り出したことを思うと、切ないです。
* 恩師のことば
2009/05/23 | Filed under アート | Tags .数日前、恩師の先生と久しぶりにお電話でお話しました。大学に通っていた頃、先生が主宰されていた洋画のアトリエで、美大を受験する高校生の子たちに混じって、デッサンを習っていたのです。
実際に習ったのは2年間、今考えると短い期間ですが、頻繁に通いました。2年目は、自分ももう一回美大に行き直そうと思って、(結局やめて金融機関に就職したのですが)ずいぶん夢中になっていたと思います。先生のアトリエはずいぶん自由な雰囲気で、先生も自分の油絵を描きながら、みんなてんでに描いて、好きなおしゃべりをして。みたいな感じでした。
先生は、最近刊行された「野の花えほん」を見てくださったのですが、おっしゃるには「上手くなったらあかんで。上手い人はようさん(←関西弁で沢山の意味)いてるからな」。
実は、このコメントは、学生の頃から繰り返し、先生に言われていて、もう無意識にインプットされています。一番最初にこの言葉を聞いたのは、「絵が下手なので上手くなりたいんです」と、習い始めの時に相談した時だったと思います。
その時は、何もわからなかったけれど、確かに、技術的に上手な描き手の方は本当に沢山存在しているので、その部分では全くわたしは太刀打ち出来ないはずでした。でも、その言葉を最初にガツンと言われていなかったら、今こんなに絵を楽しく描けるようにはなっていなかったと思うのです。
そういえば先生は、一昨年のカレンダーを見て「うっわー 下手やなあ!!」とも。正直、最近ではそんな事言われるのに慣れてないので「えっ(汗)」。
先生はつねにそんな調子で、お話すると、いつも空がさーっと晴れ渡るような小気味良さがあります。20〜21歳の本当に短い間、先生との出会いがなければ、今のような絵本や絵の仕事が出来ていなかった可能性は大。若い時にどういう大人と出会うかは、その後の人生にずいぶん影響してくるのだと 今さらながら実感します。
* しずかな一日
2009/05/15 | Filed under 音楽 | Tags 未分類.ここの所,仕事がオーバーワーク気味だったのですが,大きな仕事がひと山越えたので,きのうは思いきって1日お休みさせてもらいました。1年にたぶん数日しかないほどの,とても爽やかなお天気。そよそよと風に揺れる藤の葉を眺め、さわさわという葉ずれの音をひたすら ぼーっと聞いて午後じゅう過ごしてしまいました。
音楽も何もなしの,ひたすら静かな沈黙の中にいると すこしずつ頭も体もほぐれてくるようです。
日が暮れかけたころ,すこし元気を取り戻して来たので,音楽をかけてみました。
チェロかバイオリンのソロの演奏が好きで,よく聞きます。このようなソロ曲に共通して言えるのは、音が演奏されているのでありながら,たいへん「静寂」を感じさせてくれること。
それは,楽器の音がいっぽうにあって,それが響き渡るための「静寂」があるからだと思います。白い紙に描かれた墨絵のようなもので,墨がにじむための紙の白が存在しているというのに似ているのです。
奏でられている音楽を聞きながら、一方でその音楽を受けとめている「静寂」をあじわっているような気がします。
今日聴いていたのは,最近お気に入りのチェロのCD. 夫がitunesで購入しました。Jean-Guihen Queyrasというチェリストの演奏です。わが家では「羽賀研二みたいな人のチェロ」で話が通じてます。。(この方の別の写真を見ると、とくに羽賀研二似という訳ではないですが,この写真はよく似ているような)
* 世界はアレゴリーに満ちているから
2009/04/10 | Filed under 生活 | Tags 未分類.冬の間は、どうなることかといつも思うのですが、春のこの時期になると、何もしなくても庭の植物が自然に芽吹き、1年でいちばん美しい季節をむかえます。小さな中庭のすみっこの、まったくの日陰に植えているアケビも、たくさん花をつけてくれました。
毎年庭の小さな自然を眺めていると、人の世界に起こることと、よく似ているので不思議な気持ちになります。たとえば、はびこりすぎた古い枝をばっさり切って整理すると、下の方から若くて元気の良い芽がのびてくるとか。同じ植物ばかりが増えすぎた群落は、キャパを超えると、いっきに群落ごと枯れるとか。
こんなふうに何かを何かに喩えるのを「アレゴリー alegory=寓話,比喩」と呼ぶようです。以前養老孟司さんの本で読んだのですが、人間は大脳が発達したので、外界を直接認識するだけでなく、余った大脳で「アレゴリー」を生み出すようになったのだとか。原始的には、丸い石を見て、りんごを連想するようなことから、だんだんに脳の働きが複雑になり、複雑なアレゴリーを生み出すようになったそうです。つまり、植物を見て「人の生き方に似ているなあ」と思ったりするのは、人間の大脳の働きだということです。
つまりアレゴリーはヒトの頭の中にだけ作られているもの。でも、どうして世界にはこんなにもアレゴリーが満ちているのでしょう。そのようなことを、たまに考えます。宇宙には、何かひとつの大きな法則のようなものがあって、ヒトの大脳の中で、法則でつながるそれぞれの現象が、アレゴリーとして 串刺しのお団子のように並んでいる。。。そういうイメージが浮かんできました。これもアレゴリーなんでしょうね。
* 小島一郎写真集成
2009/04/07 | Filed under アート | Tags .10年くらい前、40歳代、50歳代の人の話を聞くと、若いころに比べて興奮したり感動したりすることが少ない。と 多くの方が仰いました。その時には、どういうことなのかよくわからなかったけれども、最近では、すこしわかる。それは、わたしにとっては いたずらに気持ちがブレない、落ち着いた心の状態とも言えるようにもおもえます。
そんな日々ですが 「興奮」「感動」をおぼえました。この写真集に出会って。
小島一郎という、青森や北海道の人や風景を撮った写真家の写真集です。39歳という若さで、1960年代に亡くなったそうですが、生前すでに有名だったらしい。亡くなった後はしばらく忘れられかけていたようですが、このたび青森で写真展が開催されたそうです。
きびしい津軽の風景や、そこに生きる人のすがたは、被写体としてとても生々しいのですが、驚く程、それが造形として昇華されています。とくに最後の方の雪の風景。コントラストの強い焼き方もあって もうほとんど抽象画に近いほど。もし、身近な人が、こんな写真を撮ってたら、「こんなに研ぎすまされてしまったら、この人もう死んでしまうのじゃないだろうか」と心配になると思います。それくらい透明感があり、息をのんでしまいました。
こんな写真、実物を見てみたいものだと、おもいます。本によると、ピューリッツァー賞をとった報道写真家(戦場カメラマン)の沢田教一は、青森で小島一郎が経営していた写真店に勤めていたことがあり、影響を受けたと書いてあったので、小島一郎のスタンスも「ドキュメンタリー」だったのかもしれません。けれども、単なるドキュメンタリーではなく造形美をとことん追求しているのが伝わって来ます。蛇足ながら、生前の写真を拝見すると、小島一郎さん、かなり男前でもあります。
かっこよすぎる写真集でした。
* 野の花えほん
2009/04/06 | Filed under 本, 花, 野の花えほん | Tags 野の花えほん.4月末に あすなろ書房から「野の花えほん」が刊行になります。ほんとうに久しぶりの絵本です。
今、表に出ると 「野の花えほん」に描いた春の花が、今年も次々花開いているのに出会います。ちょうど去年の今頃も、毎日外を出歩いては 花を採ってきて、スケッチを描いていました。
写真の 「むらさきけまん」もこの絵本に紹介した花のひとつ。以前住んでいた家の近所の空き地に咲いていたのを採ってきて、庭に植えているのです。
絵本のこと 絵のこと、思うことがたくさんありすぎて、短くまとめきれません。少しずつ、書いてみたいと思います。
* せっけん
2009/03/24 | Filed under 生活 | Tags .もう7〜8年つづいてるでしょうか、1年に1回、母校の大学に授業しに行っています。昨年末行った際、担当教授の先生に、自分が絵を描いた2009年用Panasonicのカレンダーを差し上げたら、「わあ、夢がある」と言っていただき、「はっ」としました。「夢がある」っていう表現、そういえば最近使ってなかったな と思って。
そんなことを思い出したのは、先週、恵文社生活館で、この写真の石鹸を買ってきて、洗面所のガラス瓶にしまっていた時です。LINNETの新しいシャンブレイ「トパーズ」の写真に使ったこの石鹸、手作りの天然石鹸だそうで、やさしくノーブルな自然の精油の香りです。パッケージも上品で素敵。
恵文社生活館では、前も3匹の子豚の形をしエレガントな箱に入った、とてつもなく良い香りの石鹸をみつけたのですが、そもそも石鹸って、どうしてこんなふうに「夢がある」のでしょうか。石鹸そのものが持つ、なんだかおいしそうな質感にも加えて、お洒落なパッケージ、素敵な香り、実用品である石鹸は、いつから こんなふうに「夢」をまとうことになったのか。。。考えてみると不思議だなあと。
そんなことを とりとめなく考えながら、何度も、石鹸をクンクンしてしまいました。
* いつものわたし、ナチュラルな服 (続)
2009/03/20 | Filed under アート, リネン, 動物, 本 | Tags .明日からLINNETで、「いつものわたし、ナチュラルな服」に収録の作品をセレクトして展示します。編集さんの手元から戻ってきた作品を箱から取り出していると、撮影のときのことを思い出します。
お洋服の本を作る時に、いつも悩むのがスタイリングのこと。わたしの場合、プロのスタイリストさんとは違って、特定のテーマを設定して、スタイリングを創造するような能力がありません。ですから、スタイリングと言っても、いつも結局、自分の持っているものを作品に合わせることしか出来ません。ただ、出来上がってみると、それはそれで、まぎれもない そのまんまの素の自分の世界が本になっている気がします。
今回も、学生の頃好きだった古いレコードのジャケットや、好きな洋書など、身の周りにいつもあるものを洋服に合わせました。P18,19,22に写っている植物標本は、夫の叔母が若かりし頃、留学先のアメリカの大学の授業で作ったという押し花の標本を、特にわたしに、と叔母が言ってくれて譲り受けたものです。律儀な叔母の手がき文字で、植物の名前などの情報が書き込まれたそれは数百枚もあるのですが、叔母亡き今、大切な形見でもあります。この標本自体が本当に素敵なので、額に入れようと思って出してみた所、ふと思い立って、その中の一部を服に合わせてみました。明日からの展示では、その標本もLINNETに置いて、お客様に見て頂きたいとおもっています。
撮影は去年の9月の始め頃。その頃から、うちの台所のお勝手口に、子猫が遊びに来るようになったのです。頭からおしりまでの長さが20cmくらいしかなかった子猫は、姪の持っている猫のぬいぐるみにそっくりで、姪たちがつけた、そのぬいぐるみの名前をもらって「ニャンカ」とよぶようになりました。夏の終わりで、いつも網戸にしていたお勝手口に、撮影の間もニャンカが遊びに来るので、皆さんに見てもらったりしました。
あれから7ヶ月近く。ほとんど大人に近づいたニャンカ、実は、今はうちの家族なのです。今は外にも出かけたがらなくなり、完全室内暮らしで家の中を走り回っています。他の猫3匹とも、仲良くなりました。上の写真は、本の撮影の合間に撮った、子猫時代のニャンカです。
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
New archive
BlogArchives:
- 2014 November (2)
- 2014 October (9)
- 2014 August (2)
- 2014 May (1)
- 2014 April (1)
- 2013 July (1)
- 2013 June (1)
- 2012 March (3)
- 2012 February (3)
- 2012 January (4)
- 2011 October (3)
- 2011 September (3)
- 2011 February (2)
- 2011 January (3)
- 2010 December (1)
- 2010 October (3)
- 2010 September (3)
- 2010 August (3)
- 2010 July (6)
- 2010 February (2)
- 2010 January (5)
- 2009 June (1)
- 2009 May (3)
- 2009 April (3)
- 2009 March (3)
- 2009 January (1)
- 2008 December (2)
- 2008 September (1)
- 2006 November (2)
- 2006 October (1)
- 2006 August (3)